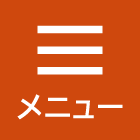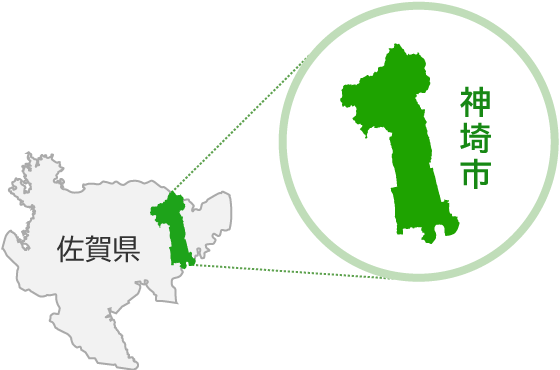猫の健康・安全と近隣の方とのトラブル防止のために適切な飼い方を心がけましょう。
1 室内飼育に努める
猫は上下運動ができる場所があり、トイレトレーニング等の必要なしつけを行えば、室内だけで飼うことが可能です。
室内で飼育すれば、交通事故やさまざまな感染症、猫同士のケンカによるケガ、猫への嫌がらせといった「猫に対する危険」を防ぐことができます。
また、近隣の方の庭にフンやおしっこをしてしまう、他人の車を傷つけてしまう、などといった「周囲の方への迷惑行為」も防ぐことができます。
猫が室内で過ごしやすい環境を整えて、室内で飼えるようにしましょう。
室内飼いのポイント
- 上下運動ができる場所
- 避妊去勢手術
- いつもきれいなトイレ
- 楽しいおもちゃ
- 新鮮な水と餌
- 飼い主の愛情とスキンシップ
2 身元の表示
万が一、猫が迷子になった場合、ケガなどをして保護をされた場合に身元の表示がなければ、猫の飼い主の方を探すことが困難です。飼い主の連絡先を書いた名札やマイクロチップをつけるようにしましょう。
迷子になってしまったら
下記の施設に問い合わせましょう。
- 神埼市役所 生活環境推進課 電話:0952−37−0112
- 神埼警察署 電話:0952−52−2114
- 佐賀中部保険福祉事務所 電話:0952−30−1906
3 避妊・去勢手術の実施
猫は1年に数回出産するため、あっという間に増えてしまいます。繁殖を望まない場合は、避妊・去勢手術を受けさせましょう。
手術を行うと発情期の鳴き声やスプレー行為の習慣とおしっこの臭いが軽減されます。
発情期特有の鳴き声やスプレー行為を防ぐためには、最初の発情期が来る前に手術をすることをおすすめします。生後6か月を過ぎたら早めに手術を受けさせるようにしましょう。
4 地域猫活動とは
地域住民が主体となり、今いる猫をこれ以上増えることがないように不妊去勢手術を実施し、餌やりやトイレ設置などのルールを定め、猫の排除に拠らないで問題解決を図る活動です。
地域猫活動の進め方
1.地域での話し合い
2.計画つくり
3.不妊去勢手術
4.餌やりやトイレなどの適正な管理
5.地域への活動報告、捨て猫防止対策
「地域猫活動」は、地域の住民の方々が主体となって取り組む活動であり、活動の成功には地域の方々の理解と協力が必要です。
猫が好きな人だけではなく、猫が嫌いな人、猫で困っている人、みなさんの協力がなくては成り立ちません。
5 猫の適正飼養ガイドライン
佐賀県では、飼い猫の正しい飼い方や飼い主の責任などを明確に示し、住民が主体となって飼い主のいない猫を適正に管理する「地域猫活動」の考え方を導入し、猫の致死処分数や猫に関するトラブルの軽減を図る目的で「猫の適正飼養ガイドライン」を作成されています。
添付ファイル
 (PDF:1.09メガバイト)
(PDF:1.09メガバイト)問い合わせ
ゼロカーボンシティ推進課 生活環境係電話:0952-37-0112