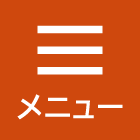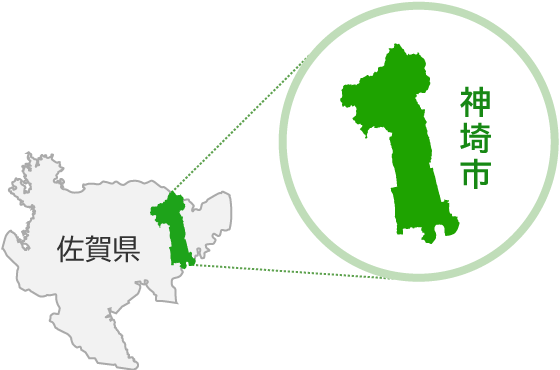県内で麻しん(はしか)の患者発生がありました。
麻しん(はしか)について
感染経路と感染可能期間
麻しん(はしか)は、飛沫感染、接触感染、空気感染により感染します。
発症した人が周囲に感染させる期間は、症状が出現する1日前から解熱後3日後です。
免疫を持っていない人が感染すると、ほぼ100%発症すると言われています。
潜伏期間
感染後、10~12日※の潜伏期間を経て、発症します。
※「修飾麻しん」の場合は、潜伏期間が14日以上になることもあります。
<修飾麻しんとは>
麻しんに対する免疫は持っているけれども不十分な人が麻しんウイルスに感染した場合、軽症で非典型的な麻しんを発症することがあります。
このような場合を「修飾麻しん」と呼んでいます。
例えば、潜伏期間が延長する、高熱が出ない、発熱期間が短い、コプリック斑が出現しない、発疹が手足だけで全身には出ない等です。
その感染力は弱いものの周囲の人への感染源になるので注意が必要です。
症状
【カタル期】
感染すると約10日後に38℃前後の発熱が2~4日間続き、咳、鼻水、結膜充血、目やになどがみられ、乳幼児では8~30%に消化器症状として下痢や腹痛を伴います。発疹出現の1~2日前頃に頬粘膜に白色の斑点(コプリック斑)が出現します。
【発疹期】
カタル期での発熱が1℃程度下降した後、半日くらいのうちに再び高熱(多くは39.5℃以上)が出るとともに、特有の発疹が耳の後ろ、首、顔、体、上腕、下肢の順に広がります。発疹が全身に広がるまで、発熱(39.5℃以上)が3~4日間続きます。
【回復期】
発疹出現後、3~4日間続いた発熱も回復期に入ると解熱し、全身状態が改善し、発疹も退色してきます。
※合併症
脳炎、中耳炎を合併しやすく、また、10万人に1人程度と頻度は高くないものの、麻しんウイルスに感染後、特に学童期に亜急性硬化性全脳炎(SSPE)と呼ばれる中枢神経疾患を発症することがあります。
予防
麻しんは感染力が強く、空気感染もするので、手洗い、マスクのみでは予防はできません。麻しんワクチンの予防接種が最も有効な方法といえます。麻しんワクチンの定期接種の対象者※の方は、早めに予防接種を受けましょう。
※麻しんワクチンの定期接種の対象者
第1期:1歳児(生後12月から生後24月に至るまでの間にある方)
第2期:小学校入学前の1年間(5歳以上7歳未満であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当
該始期に達する日の前日までの間にある方)
定期接種の対象者以外の方でも、以下に該当しない方は、麻しんワクチンの接種をご検討ください。
-
母子健康手帳などで麻しんワクチンを2回以上受けた記録がある
-
過去に麻しん(はしか)にかかったことがある(検査で麻しんと確認されたことがある)
なお、定期予防接種の対象でない方は、任意接種(有料)となります。
また、麻しんワクチンは妊娠している女性は接種を受けることができませんし、妊娠されていない場合であっても、
接種後2か月程度の避妊が必要となります。
医療機関の皆様へ
発熱や発疹を呈する患者を診察した際は、麻しんの可能性を念頭に置き、海外渡航歴及び国内旅行歴を聴取し、麻しんの罹患歴及び予防接種歴を確認するなど、麻しんを意識した診療をお願いします。
麻しんと診断した場合には、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の第12条第1項の規定に基づき、都道府県知事(最寄りの保健福祉事務所)へ速やかに届け出るとともに、麻しんの感染力の強さに鑑みた院内感染予防対策の実施をお願いします。
参考資料
問い合わせ
こども家庭課 母子保健係電話:0952-37-3873