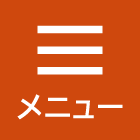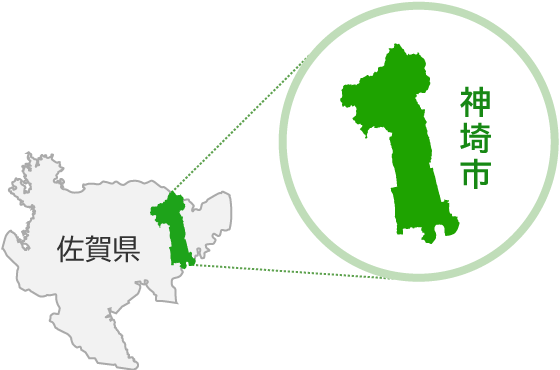国民健康保険に加入する方
勤務先の健康保険に加入している人、生活保護を受けている人、児童福祉施設に入所していて扶養義務者がいない人以外で、75歳未満のすべての人は、国民健康保険に加入しなければなりません。ただし、65歳以上75歳未満で一定の障害のある方は、後期高齢者医療へ加入できます。
※75歳以上のすべての方は、後期高齢者医療に加入します。
外国人の方の国民健康保険の加入
神埼市にお住まいの外国人の方は、次のいずれかに該当する方を除き、国民健康保険に加入しなければなりません。
・在留期間が3か月以下の方
※在留期間が3か月以下でも、在留資格が「興行」、「技能実習」、「家族滞在」、「公用」、「特定活動(医療を受ける活動等、観光・保養を目的とする活動等を除く)」の場合で、資料等により3か月を超えて滞在すると認められる方は加入できます。
・在留資格が「短期滞在」、「外交」の方
・在留資格が「特定活動」のうち、「医療を受ける活動またはその方の日常の世話をする活動の方」、「観光、保養その他これらに類似する活動を行う方またはその方と同行する配偶者の方」
・日本と医療保険を含む社会保障協定を結んでいる国の方で、本国政府からの社会保険加入証明書(適用証明書)の交付を受けている方
・会社等の健康保険に加入している方
・後期高齢者医療保険の被保険者の方
・生活保護を受けている方
異動の届け出は
国保に加入するとき、 やめるときは 14日以内に届け出が必要です。
加入の届け出が遅れると、加入資格を得た月までさかのぼって保険税を納めなければならなくなります。
また、資格確認書または資格情報のお知らせ(以下、「資格が確認できる書類」という)がないため、その間にかかった医療費は全額自己負担となるので、ご注意ください。
国保に加入するときは?
| 他の市区町村から転入してきたとき | 他の市区町村の転出証明書 |
|---|---|
| 職場の健康保険などをやめたとき | 社会保険喪失証明書または離職票 |
| 職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき | 被扶養者でない理由の証明書 |
| 子どもが生まれたとき | 資格が確認できる書類、母子健康手帳 |
| 生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 |
国保をやめるときは?
| 他の市区町村へ転出するとき | 資格が確認できる書類 |
|---|---|
| 職場の健康保険に加入、 または被扶養者になったとき |
国保、職場の健康保険の両方の資格が確認できる書類(職場の資格情報がわかる書類が未交付の場合は加入した証明) |
| 国保の被保険者が死亡したとき | 資格が確認できる書類、死亡を証明するもの |
| 生活保護を受けるようになったとき | 資格が確認できる書類、保護開始決定通知書 |
その他
| 市内での転居で住所の変更や、 世帯主の変更、世帯分離、合併したとき |
資格が確認できる書類 |
|---|---|
| 修学のため、別に住所を定めるとき | 資格が確認できる書類、在学証明書 |
| 資格確認書または資格情報のお知らせを紛失、汚損したとき | 身分を証明するもの、汚損した資格が確認できる書類 |
資格が確認できる書類を使うと
診療を受けたときにかかった費用の2割〜3割は、被保険者は一部負担金として支払い、残りの7割〜8割を国保が負担します。又、何らかの理由で資格が確認できる書類を提示できなかったときは、一度、全額を支払った後で領収書と診療内容証明書を添えて申請すると審査のうえ、医療費総額の7割〜8割をお返しします。
高額療養費
病気やけがで医療機関等を受診・入院し、月の1日から末日(暦月)までの1か月に支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が高額療養費として国民健康保険から支給されます。高額療養費の支給対象となる世帯には、診療後の2か月後以降に申請書をお送りします。申請書が届きましたら、郵送もしくは窓口にて申請してください。
自己負担限度額
70歳未満の人
| 区分 | 限度額 | ||
|---|---|---|---|
| ア | 年間所得※1 901万円超 |
252,600円+(実際の医療費-842,000円)×1% (4回目からは140,100円) ※2 |
|
| イ | 年間所得 600万円超〜901万円以下 |
167,400円+(実際の医療費-558,000円)×1% (4回目からは93,000円) |
|
| ウ | 年間所得 210万円超〜600万円以下 |
80,100円+(実際の医療費-267,000円)×1% (4回目からは44,400円) |
|
| エ | 年間所得 210万円以下 |
57,600円(4回目からは44,400円) | |
| オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円(4回目からは24,600円) | |
※1 年間所得とは、総所得金額から基礎控除額を差し引いた額です。
※2 直近12か月間に4回以上払い戻しを受けるときは、4回目から限度額が下がります。
70~74歳の人
| 区分 | 限度額 | ||
|---|---|---|---|
| 外来限度額(個人ごとに計算) | 外来+入院および世帯の限度額 | ||
| 課税所得690万円以上 | 252,600円+(実際の医療費-842,000円)×1% (4回目からは140,100円) ※3 | ||
| 課税所得380万円以上690万円未満 | 167,400円+(実際の医療費-558,000円)×1% (4回目からは93,000円) | ||
| 課税所得145万円以上380万円未満 | 80,100円+(実際の医療費-267,000円)×1% (4回目からは44,400円) | ||
| 一般 | 18,000円 (年間上限14万4千円) | 57,600円(4回目からは44,400円) | |
| 低所得者 | II ※1 | 8,000円 | 24,600円 |
| I ※2 | 15,000円 | ||
※1 低所得者IIとは、世帯主と世帯全員が住民税非課税の世帯の人。
※2 低所得者Iとは、世帯主と世帯全員が住民税非課税で、かつ、各種収入から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯の人。
※3 直近12か月間に4回以上払い戻しを受けるときは、4回目から限度額が下がります。
入院時の食事代
入院したときの食事代は、次の標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。
入院時の食事代の標準負担額
| 区分 | 1食あたりの食事代 | |
|---|---|---|
| 下記区分以外の人 | 510円(下記以外の指定難病の人は300円) | |
| 住民税非課税世帯 低所得者II |
90日までの入院 | 240円 |
| 90日を超える入院 (過去12か月の入院日数) |
190円 | |
| 低所得者I | 110円 | |
※住民税非課税世帯と低所得者I・IIの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」か「標準負担額減額認定証」が必要です。国保の窓口に申請してください。
※マイナ保険証をお持ちの方で、オンライン資格確認によって限度額適用区分を確認できる場合は、認定証がなくても減額されます。
※90日を超える入院となった場合は、認定証を切り替える手続きが必要です。
※入院時の食事代は、高額療養費の対象となりません。
療養病床に入院する65歳以上の人
療養病床に入院する65歳以上の人は、次の標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。
| 区分 | 1食あたりの食事代 | 1日あたりの居住費 |
|---|---|---|
| 下記区分以外の人 | 510円(下記以外の指定難病の人は300円) | 370円 |
| 住民税非課税世帯 低所得者II |
240円(医療の必要性の高い人・指定難病の人で90日を超える入院は190円) | |
| 低所得者I | 140円(医療の必要性の高い人・指定難病の人は110円) |
※住民税非課税世帯と低所得者I・IIの人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。国保の窓口に申請してください。
※マイナ保険証をお持ちの方で、オンライン資格確認によって限度額適用区分を確認できる場合は、認定証がなくても減額されます。
※指定難病の人は、食事代のみの負担です。
高額療養費の計算上の注意
入院時の食事代や差額ベッド代、保険医療の対象外の治療費などは、高額療養費の対象になりません。ご不明な点は、担当係までお問い合わせください。
出産・死亡したとき
国民健康保険に加入されている人が出産・死亡された際は、出産育児一時金・葬祭費が支給されます。
また、出産された方については、産前産後期間における国民健康保険税が免除されます。(いずれも申請が必要です)
出産育児一時金の支給
加入者に子どもが生まれたとき支給されます。
(妊娠12週以上の死産・流産を含む)
産前産後期間における国民健康保険税の免除
産前産後期間の4か月(多胎の場合は6か月)相当分の所得割額と均等割額が免除されます。
(死産・流産・早産および人工妊娠中絶の場合も含む)
葬祭費の支給
加入者が死亡したとき、葬儀を行った人(喪主)に支給されます。
交通事故等にあったとき(第三者行為)
交通事故など、第三者(加害者)の行為が原因となったけがや病気の医療費は、原則として加害者が負担すべきものです。第三者行為による傷病の治療にも国民健康保険を使用することができますが、その場合は、警察が発行する事故証明書を添付して、「第三者行為による傷病届」等の必要書類を提出してください。
※書類をすぐに提出できないときは、取り急ぎ事故等の状況をご連絡ください。
仕事中にけがをしたとき
業務中のけがや病気は、本来労災保険の対象であり、原則として国民健康保険の給付は受けられません。
海外で治療を受けたとき
海外療養費
海外渡航中に急な病気やけがでやむを得ず現地で治療を受けた場合、海外で支払った医療費の一部の払い戻しを受けることができます。
日本国内で同様の病気やけがをして国民健康保険で治療を受けた場合にかかる治療費を基準に計算した額(実際に海外で支払った額の方が低いときはその額)から、自己負担額を差し引いた額を支給します。(支給額算定の際には、支給決定日の海外為替換算率が用いられます。)
ただし、治療目的での渡航の場合、日本で保険適用されていない治療を受けた場合、交通事故やけんかなど第三者行為による病気・けがなどは、保険給付の対象とはなりません。
必要書類
・療養費支給申請および請求書
・同意書
・診療内容明細書(FormA)(海外の医師が記入、署名したもの)
・領収明細書(医科・歯科)(FormB)(海外の医師が記入、署名したもの)
・上記2点の日本語訳(翻訳者の氏名、住所、電話番号も記載)
・海外の医療機関に支払った領収書
・国民健康保険の資格が確認できる書類
・パスポート
・印鑑
・世帯主名義の通帳
※診療内容明細書、領収明細書、領収書、日本語訳文等を発行するために必要となる費用は、申請者の負担となります。
※提出書類の記載内容に不備・不明な点がある場合は、書類の内容について詳しく内容を確認させていただきます。
一部負担金の減免および徴収猶予
災害などの特別な事情により一時的に生活が困窮し、医療費の支払いが困難なときは、申請により医療費の一部負担金が減免または徴収猶予される場合があります。
対象となる場合
・震災、風水害、火災等により死亡し、または心身に障害を受けたとき
・震災、風水害、火災等により資産に重大な損害を受けたとき
・干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作等の理由により収入が著しく減少したとき
・事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
・上記に掲げる理由に類する理由があったとき
※ただし、医療費の一部負担金が減免または徴収猶予されるためには基準等があります。詳しくは担当係までお問い合わせください。
各種申請書ダウンロードはこちら
| 資格取得届 |  PDF(116KB) PDF(116KB) |
 Excel(19KB) Excel(19KB) |
| 資格喪失届 |  PDF(114KB) PDF(114KB) |
 Excel(18KB) Excel(18KB) |
| 資格喪失証明書 |  PDF(59KB) PDF(59KB) |
 Excel(14KB) Excel(14KB) |
| 限度額・標準負担額認定申請書 |  PDF(40KB) PDF(40KB) |
 Excel(20KB) Excel(20KB) |
| 療養費支給申請および請求書 |  PDF(66KB) PDF(66KB) |
 Word(18KB) Word(18KB) |
| 標準負担額差額支給申請および請求書 |  PDF(98KB) PDF(98KB) |
 Word(17KB) Word(17KB) |
| 送付先変更届 |  PDF(78KB) PDF(78KB) |
 Word(17KB) Word(17KB) |
| 第三者行為様式:傷病届(交通事故) |  PDF(112KB) PDF(112KB) |
 Word(71KB) Word(71KB) |
| 第三者行為様式:傷病届(交通事故以外) |  PDF(113KB) PDF(113KB) |
 Word(75KB) Word(75KB) |
| 第三者行為様式:事故発生状況報告書(交通事故) |  PDF(90KB) PDF(90KB) |
 Word(145KB) Word(145KB) |
| 第三者行為様式:事故発生状況報告書(交通事故以外) |  PDF(29KB) PDF(29KB) |
 Word(32KB) Word(32KB) |
| 第三者行為様式:念書兼同意書 |  PDF(68KB) PDF(68KB) |
 Word(36KB) Word(36KB) |
| 第三者行為様式:誓約書 |  PDF(52KB) PDF(52KB) |
 Word(37KB) Word(37KB) |
| 海外療養費:同意書 |  PDF(68KB) PDF(68KB) |
 Word(17KB) Word(17KB) |
| 海外療養費:診療内容明細書(FormA) |  PDF(8KB) PDF(8KB) |
|
| 海外療養費:領収明細書(FormB)医科 |  PDF(10KB) PDF(10KB) |
|
| 海外療養費:領収明細書(FormB)歯科 |  PDF(12KB) PDF(12KB) |
|
| 海外療養費:明細書の日本語訳(FormA) |  PDF(32KB) PDF(32KB) |
|
| 海外療養費:明細書の日本語訳(FormB)医科 |  PDF(32KB) PDF(32KB) |
|
| 海外療養費:明細書の日本語訳(FormB)歯科 |  PDF(31KB) PDF(31KB) |
問い合わせ
神埼市役所 市民課 保険医療係 電話:0952-37-0115
千代田支所 総合窓口課 総合窓口班 電話:0952-44-3071
脊振支所 総合窓口課 総合窓口班 電話:0952-59-2111