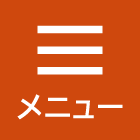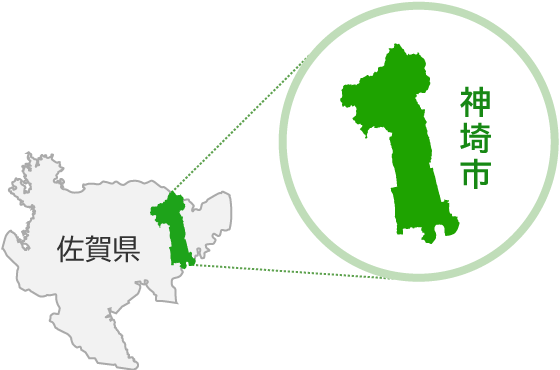国民年金制度は、老後だけでなく万が一の障害や死亡の際に、所得保障を行い国民生活の安定を図るものです。又、この制度はすべての国民を対象とし、現役世代が高齢者を支えるいわゆる「世代間扶養」の仕組みにより国民全体が助け合う制度です。
第1号被保険者
20歳以上60歳未満の自営業者・農林漁業者・学生・無職の方とその配偶者
加入の手続き先
各庁舎窓口で行います。
保険料の納め方
日本年金機構から送付される納付書で、金融機関、農協、郵便局、コンビニエンスストア等で納めます。また、指定した金融機関や郵便局から口座振替で納めることもできます。
付加年金(保険料)
定額保険料に、付加保険料月額400円を上乗せして納めることで、受給する年金額を増やせます。
老齢基礎年金に次の式で計算した額が加算されます。
付加年金額=200円×付加保険料納付月数
国民年金基金に加入される方へ
国民年金基金の1口目には国民年金の付加年金400円部分が含まれており、将来、付加年金の給付を受けることとなります。
そのため、国民年金基金と重複して国民年金の付加年金に加入することはできません。
制度については、全国国民年金基金のホームページhttps://www.zenkoku-kikin.or.jp/(外部リンク)でご確認ください。
第2号被保険者
厚生年金・共済組合に加入されている会社員・公務員の方
加入の手続き先
勤務先で行います。厚生年金や共済組合の加入手続きをすると、国民年金にも第2号被保険者として加入することになります。
保険料の納め方
厚生年金や共済組合などの保険料は、事業所を通じて納めます。国民年金保険料は、厚生年金・共済組合の保険料に含まれています。
第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者
加入の手続き先
配偶者の勤務先を通じて行います。
保険料の納め方
個人で納める必要はありません。国民年金保険料は、配偶者の加入している年金制度が負担します。
任意加入被保険者
希望して国民年金に加入することができます。
- 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人
- 海外に在住の20歳以上65歳未満の人
- 昭和40年4月1日以前に生まれた人で65歳に達しても年金受給資格を満たしていない人は、受給権を得るまで加入できます。(ただし、70歳になるまで)
ライフスタイルが変わったら必ず届け出を!
届け出の内容により、届け出先が異なりますのでご注意ください。届け出には年金手帳のほかに添付書類が必要な場合がありますので、届け出をする前にご確認ください。手続きをしないでそのままにしておくと将来年金が受けられなくなる場合がありますので、人生の節目には必ず届け出をしましょう。
届け出先 本庁または各支所
| 届け出の必要なとき | このような被保険者になります | 必要なもの |
|---|---|---|
| 20歳になったとき (すでに2号被保険者になっている人を除く) |
第1号被保険者 |
学生の場合は学生証 |
| 会社を退職したとき (厚生年金や共済組合の加入者でなくなったとき) |
第1号被保険者 | 基礎年金番号がわかるもの、離職日がわかる証明 |
| 配偶者の健康保険の扶養から外れたとき (離婚したとき・収入が増えたとき) |
第1号被保険者 | 基礎年金番号がわかるもの、扶養喪失日がわかる証明 |
届け出先 配偶者の勤務先
| 届け出の必要なとき | このような被保険者になります | 必要なもの |
|---|---|---|
| 配偶者の健康保険の扶養になったとき (結婚したとき・収入が減ったとき) |
第3号被保険者 | 詳しい添付書類は配偶者の勤務先にお尋ねください。 |
保険料を納めるとき
| 保険料を納めるとき | このような手続きがあります | 届け出先 |
|---|---|---|
| 口座振替を開始・停止するとき | 口座振替納付依頼(停止)の申し出 | 市役所および各金融機関 |
| 納付書を紛失したとき | 納付書の再発行 | 年金事務所 |
任意加入ができるとき
| 任意加入ができるとき | 届け出先 |
|---|---|
| 海外に居住する | これから海外へ転居される方→市役所窓口 現在海外に居住されている方→日本国内の最後の住所地を管轄する年金事務所窓口 |
| 60歳~65歳になるまで | 本庁または各支所 |
| 65歳~70歳になるまで | 本庁または各支所 |
保険料について
保険料は2年を過ぎると納付できなくなり、年金がもらえなくなったり年金額が少なくなったりします。忘れずに納めましょう。
忙しくて、つい納め忘れてしまうという方には、口座振替が便利です。
さらに、1年もしくは半年、2年等の前納制度もあります。この方法ですと、保険料が割引されますので、大変お得です。
保険料免除制度とは
失業して収入がない、災害などで大きな被害を受けた等、さまざまな理由により納められないときは、保険料の免除制度があります。
申請日より、原則2年1か月前までさかのぼって申請できます。
全額免除・一部免除
本人、世帯主、配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合は、申請により保険料の納付が全額免除または一部免除になります。
納付猶予
50歳未満の方で、本人、配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合は、申請により保険料の納付が猶予されます。
※免除された期間は10年以内であれば、さかのぼって納付することができます。(ただし、3年目以降は加算額がつきます。)
学生納付特例
学生の方で、本人の前年所得(1月から3月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合は、申請により保険料の納付が猶予されます。
法定免除
障害者年金を受けている方や、生活保護法による生活扶助を受けている方は、届け出をすれば、保険料の全額免除を受けることができます。
産前産後期間の保険料免除制度
対象者は、国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方です。
免除期間は、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間です。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいい、死産、流産、早産された方を含みます。
出産予定日の6か月前から届け出が可能です。
出産前に届け出をする場合は、母子健康手帳など出産予定日が分かるものが必要です。出産後に届け出をする場合は、市町村で確認できるため書類の添付は原則不要です。ただし、被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類の添付が必要です。
受けられる年金の種類
老齢基礎年金
資格期間が25年から10年に短縮
これまでは、老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。
平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになりました。
年金を受けられる場合
原則として、保険料を納めた期間と免除された期間および合算対象期間を合わせた資格期間が10年以上ある人が、65歳に達したときに支給されます。希望によって60 歳から繰上げ請求もできますが、支給額が減額になります。また、65歳になっても年金を受けないで、年齢を繰下げて受けることもできます。
年金の請求先
- 第1号被保険者期間のみの方 → 本庁または各支所
- 第3号被保険者期間を含む方 → 年金事務所
障害基礎年金
年金を受けられる場合
国民年金の被保険者期間中に、病気やけがなどで障害者になったときに支給されます。保険料の納付状況や、障害の程度も要件となります。
年金の請求先
- 診断書の初診日が第1号被保険者のとき → 本庁または各支所
- 診断書の初診日が第3号被保険者のとき → 年金事務所
- 20歳前に障害者になった場合 → 本庁または各支所
遺族基礎年金
被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たしている人などが死亡したときに、その人に生計を維持されていた18歳未満の子どもがいる場合に支給されます。(子どもが障害者の場合は、20歳未満)
寡婦年金
第1号被保険者として老齢基礎年金を受ける資格を持つ人が年金を受けずに死亡したとき、その妻に60歳から65歳になるまで支給されます。(婚姻期間が10年以上あるときに限ります。又、その妻がすでに国民年金の繰上げ請求をしている場合は、受けられません。)
死亡一時金
第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、年金を受けずに亡くなり、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。支給額は、保険料納付済期間(および免除期間)によって違います。
※寡婦年金を希望した場合は、死亡一時金は受けられません。
年金受給者の方は
住所を変更したとき、年金の受取口座を変更したとき、年金受給者が死亡したとき、年金証書をなくしたとき等、忘れずに届けてください。
また、年金を受けている方の所在が1月以上明らかでないときは、その世帯の世帯員の方は所在不明についての届け出を速やかに行う必要があります。提出先はお近くの年金事務所です。
問い合わせ
市民課 総合窓口班電話:0952-37-0116